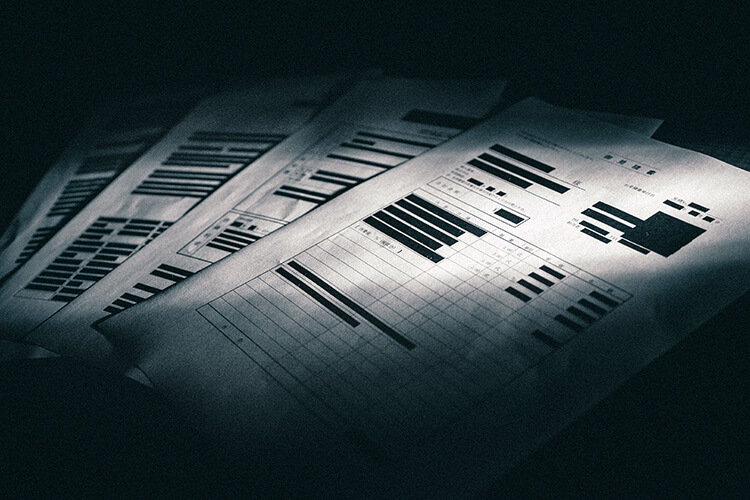
ども、ワイ氏は20代の駆け出しAIエンジニア。根性だけは誰にも負けへんって自負してる。
今日はな、転職活動をやってて人生で初めて「技術面接」ってやつに挑んできたんや。
正直、めっちゃ緊張した。でも、終わってみたら「ワイ、ようやったな」って思える一日になったわ。
ほな、どんなことがあったか、順を追って書いていくで。
技術面接のきっかけは突然に
きっかけは、転職サイトで見つけたAIスタートアップの求人やった。
「自然言語処理に強いエンジニア募集」って書いてあって、ワイのスキルとはまだちょっと差があるかな〜って思ったけど、どうしても挑戦してみたくて応募してみたんや。
そしたら、書類選考通過のメールが来て、「技術面接を受けていただきます」って。
うわ〜、ほんまに来てもうた…って思ったけど、ここで逃げたらワイの根性が泣く。せやから、全力で準備することにしたんや。
技術面接の準備
まずは、過去の面接質問をネットで調べまくった。
「Pythonの基礎」「機械学習のアルゴリズム」「データ前処理」「モデル評価」など出そうなとこは全部復習した。
あと、GitHubに上げてた自分のプロジェクトを見直して、「このコード、説明できるか?」って自問自答した。
Qiitaにも記事書いてたから、それも読み返して、「ワイは何を学んで、どう成長したんか」を整理したんや。
面接前日は、模擬面接を自分でやってみた。鏡の前で「このプロジェクトでは、BERTを使って感情分析を行いました」って練習してたら、家族に「何ブツブツ言うてんの?」って笑われたけど、気にせえへん。ワイは本気やったからな。
技術面接本番
面接当日は、朝から緊張で胃がキリキリしてた。
でも、スーツ着て、PC開いて、Zoomのリンクにアクセスした瞬間、「やるしかない」ってスイッチ入ったわ。
面接官は30代くらいの男性で、めっちゃ落ち着いた雰囲気。「じゃあ、まず自己紹介からお願いします」って言われて、ワイは準備してた通りに話した。
「ワイは、AIエンジニアとして駆け出しですが、自然言語処理に興味があり、個人で感情分析や文書分類のプロジェクトを進めてきました。根性だけは誰にも負けません!」
ちょっと関西弁混じってもうたけど、面接官は笑ってくれて、「いいですね、熱意が伝わります」って言うてくれた。ちょっとホッとしたわ。
技術質問は容赦ない
次に来たんは、技術質問や。
「機械学習モデルの過学習を防ぐ方法は?」
「BERTとWord2Vecの違いを説明してください」
「このコードのバグを見つけてください」
うわ〜、来た来た来た!って感じやったけど、ワイは冷静に答えた。
「過学習を防ぐには、正則化やドロップアウト、交差検証などが有効です」
「Word2Vecは静的な単語ベクトルを生成しますが、BERTは文脈に応じた動的な表現を出力します」
コードのバグも、ちょっと時間かかったけど、「このループのインデックスが間違ってます」って指摘できた。
面接官が「よく気づきましたね」って言うてくれて、めっちゃ嬉しかったわ。
最後に聞かれた「あなたは何を目指してますか?」
面接の最後に、「あなたはAIエンジニアとして、どんなことを目指してますか?」って聞かれたんや。
ワイは、ちょっと考えてからこう答えた。
「ワイは、AIを使って人の感情や思考を理解できるような技術を作りたいです。人と人とのコミュニケーションをもっと豊かにするために、自然言語処理を極めたいと思ってます。まだまだ未熟ですが、根性と情熱はあります!」
面接官は、ちょっと黙ってから「いいですね。そういうビジョンを持ってる人は、成長が早いです」って言うてくれた。ワイ、心の中でガッツポーズしたで。
技術面接を終えた感想
面接終わった瞬間、めっちゃ疲れたけど、同時に「ワイ、ようやった!」って思えた。緊張もあったし、答えに詰まったとこもあったけど、全力でぶつかったことに後悔はない。
今回の面接で学んだことはいっぱいあるけど、特に大事やと思ったんはこれや
技術だけやなくて、熱意とビジョンも伝えること
準備は裏切らへん。やった分だけ自信になる
面接官も人間。素直に話すことが大事
面接の結果はまだ出てへん。でも、ワイはもう次に向けて動き出してる。
今回の経験を糧にして、もっと技術磨いて、もっと自分の言葉で語れるようになりたい。
もし落ちたとしても、それは「次の挑戦へのステップ」や。ワイは前向きに、根性で進んでいくで!
アニメ・漫画の登場人物やゲームキャラクターの現在の年齢まとめ
X(旧Twitter)やYouTube、TikTok、SNSで話題の猫(ネコ、ねこ)情報まとめ
犬(ワンちゃん)を飼っている意外な有名人・タレント・芸人・インフルエンサー・YouTuberまとめ
TikTokで人気急上昇のTikToker(ティックトッカー)情報まとめ
スポンサーリンク
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d95674f.5ea53f98.4d956750.ba046f97/?me_id=1285657&item_id=12998944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01141%2Fbk4046071877.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

