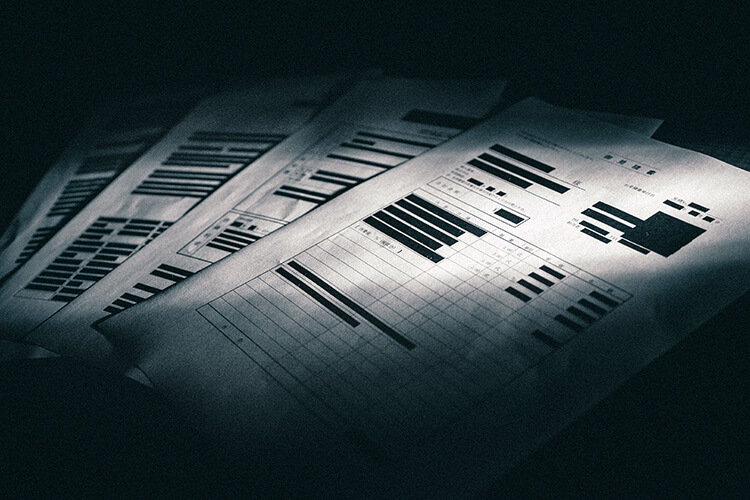
ワイは都内在住の30代、現役のAIエンジニアや。
普段は某IT企業で自然言語処理のモデル開発に携わっとる。
仕事は面白いし、技術的にもやりがいある。
でも、正直言うて、会社の給料だけで将来安泰とは思えへん。
副業で収入の柱をもう一本作りたい、そんな思いがずっとあった。
副業って言うても、ワイは営業もせえへんし、動画編集も苦手や。
せやから「自分の得意分野で勝負するしかない」と思って、AI関連の知識を活かす方法を探し始めた。
アイデアの着想
ある日、Xで「AI活用事例まとめました」っていうnote記事がバズってるのを見た。
内容は、ChatGPTを使って業務効率化した事例とか、画像生成AIでSNS運用してる人の話とか。
ワイはそれを読んで、「これ、ワイの方がもっと深く書けるやん」って思った。
ワイは日々、社内外のAI活用事例を見てるし、実際にクライアント向けにPoC(概念実証)もやってる。
その経験を活かして、「AI活用のケーススタディ集」を作って販売することにしたんや。
ターゲットは、AIに興味あるけど実際にどう使えばええか分からん人。
中小企業の経営者、フリーランス、マーケター、教育関係者。
そういう人らに向けて、「実際に使えるAI活用事例」をまとめたら価値あると思った。
コンテンツ制作と販売戦略
まずは構成を考えた。ケーススタディは全部で10本。ジャンルは以下の通りや。
ChatGPTを使った業務マニュアルの自動生成
Midjourneyによる商品画像の作成
Notion AIで議事録の要約
Whisperで音声データの文字起こし
GPTで営業メールの自動作成
AIによるSNS投稿の最適化
教育現場でのAI教材作成
小規模ECサイトでのAIチャットボット導入
AIによる市場調査の自動化
自営業者向けのAI事務処理支援
それぞれの事例に、導入背景、使用ツール、プロンプト例、成果、注意点をまとめた。
ワイは実際に使ったツールのスクリーンショットも添えて、読者がすぐに真似できるようにした。
販売はnoteで行った。
タイトルは「現役AIエンジニアが教える!実践AI活用ケーススタディ10選」。価格は1,980円。
最初は高いかなと思ったけど、内容に自信あったし、安売りする気はなかった。
初動と反応
noteを公開して、Xで告知した。
「AI活用に悩んでる人へ。実際に成果出た事例をまとめました」って感じで投稿したら、フォロワーから「これは欲しい!」って反応があって、初日に10部売れた。
その後も、AI関連のコミュニティで紹介してもらったり、noteのランキングに載ったりして、1週間で50部突破。
売上は約10万円。ワイは自宅のデスクで、コーヒー飲みながら「マジで副業ってできるんやな…」ってしみじみ思った。
購入者の声とリピート戦略
購入者からは「具体的で分かりやすい」「すぐに業務に活かせた」「プロンプト例がありがたい」って声が届いた。
ワイはそれをnoteの紹介文に追記して、さらに信頼感を高めた。
また、購入者向けに「続編希望アンケート」も実施した。
結果、「もっと業種別の事例が知りたい」「教育分野に特化したケーススタディが欲しい」って声が多かった。
そこで、ワイは「教育業界向けAI活用事例集」と「マーケティング業界向けAI活用事例集」の制作を決意。
これが次の副業展開につながることになる。
副業を通じて得たもの
この副業を通じて、ワイは「知識は資産になる」ってことを実感した。
普段の仕事では社内のプロジェクトに閉じた知識やけど、それを外に出して、困ってる人の役に立てることで、収益にも繋がる。
また、読者とのやり取りを通じて、AIの活用ニーズや現場の課題も見えてきた。これは本業にも活かせる視点やと思う。
今では、ケーススタディ集の販売はワイの副業の柱になってる。
もちろん、まだまだ改善点はあるし、収益も安定してるわけやない。
でも、「自分の知識で人を助けて、収入も得られる」って体験は、何にも代えがたい価値や。
こんな感じで、ワイの副業ストーリーは続いてる。
次の目標は、月収20万円。
そして、いずれは「AI活用のオンライン教材」も作って、もっと多くの人に届けたいと思ってる。
ワイみたいな普通のエンジニアでも、ちょっとした工夫と行動で副業はできる。
もしこの記事を読んで「自分もやってみたい」と思ったら、ぜひ一歩踏み出してみてや。
アニメ・漫画の登場人物やゲームキャラクターの現在の年齢まとめ
X(旧Twitter)やYouTube、TikTok、SNSで話題の猫(ネコ、ねこ)情報まとめ
犬(ワンちゃん)を飼っている意外な有名人・タレント・芸人・インフルエンサー・YouTuberまとめ
TikTokで人気急上昇のTikToker(ティックトッカー)情報まとめ
スポンサーリンク
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d95674f.5ea53f98.4d956750.ba046f97/?me_id=1285657&item_id=12998944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01141%2Fbk4046071877.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

