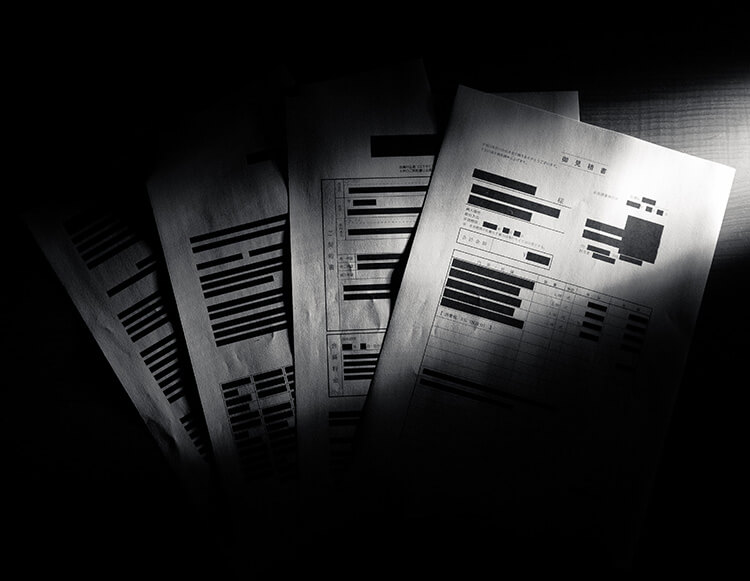
ワイは都内在住の30代、現役のAIエンジニアや。
普段は某IT企業で自然言語処理(NLP)や機械学習モデルの開発を担当してる。
仕事はおもろいし、やりがいもある。
でも、会社の枠だけで生きるのはもったいない気がしてて、副業で自分のスキルを試すのが趣味みたいになってる。
そんなある日、LinkedInで「営業用AIデモを作れる人を探しています。報酬10万円、納期2週間」っていう投稿を見つけた。
ワイ、思わず「これ、ワイの出番やん」と声出たわ。営業用のAIデモって、要はクライアント向けに見せる“動くサンプル”やろ?ワイ、社内でもよう作ってるし、得意分野や。
案件との出会い
投稿主にDM送ったら、すぐに返信が来た。
相手はSaaS系のスタートアップで、営業チームがAIを使った提案をしたいけど、技術的なデモが作れへんらしい。
社内にエンジニアはおるけど、営業向けの“見せるAI”を作れる人がいないとのこと。
「営業先で『こんなことできますよ』って見せられるAIデモを作ってほしい。できれば、Webブラウザで動くやつ。報酬は10万円でどうですか?」
ワイは即答した。「やります」
要件の整理
まずはZoomでヒアリング。営業先は製造業の企業で、品質管理や異常検知に興味があるらしい。
せやから、AIで「異常なデータを検知する」っていうデモを作ってほしいとのこと。
しかも、営業がノートPCで開いて、ブラウザでサクッと見せられるようにしてほしいらしい。
要件はこんな感じや
Webブラウザで動くAIデモ
製造業のセンサーデータを模したCSVを読み込んで、異常値を検知
検知結果をグラフで表示
UIはシンプルで、営業が説明しやすいように
コードはGitHubで納品、ドキュメント付き
ワイは「これはStreamlit+異常検知モデルでいけるな」と判断。
実装と工夫
まずは、センサーデータっぽいCSVを自作。
温度、圧力、振動みたいな項目を入れて、異常値をランダムに混ぜた。
モデルはIsolation Forestを使って、異常スコアを算出。
StreamlitでUIを作って、CSVをアップロード→グラフ表示→異常箇所を赤でハイライトするようにした。
一番工夫したのは、営業が説明しやすいように「この赤い点が異常です」「正常な範囲はここです」っていう注釈をグラフに入れたことや。
あと、モデルの仕組みを簡単に説明するセクションも追加して、「AIがどう判断してるか」を営業が語れるようにした。
さらに、デモの起動方法をREADMEに丁寧に書いて、営業が技術に詳しくなくても使えるようにした。
ワイは「技術は見せ方が命や」と思ってるから、見た目と使いやすさにはこだわった。
自宅での作業
作業は全部自宅でやった。平日は仕事終わってから、夜に2〜3時間。週末は朝からコーヒー飲みながらがっつり。
Streamlitは軽いから、ローカルでサクサク動くし、開発も快適やった。
嫁には「またパソコンばっかりやな」って言われたけど、ワイは「これで10万やからな」とニヤけてた。
副業って、報酬も嬉しいけど、自分のスキルが誰かの役に立つって実感できるのがええんよな。
納品と報酬
納期の2日前にGitHubでコードとREADMEを納品。
Zoomでデモを見せたら、営業チームの人が「これ、めっちゃ使いやすい!説明もしやすい!」って喜んでくれた。
即日で報酬の10万円が振り込まれた。ワイ、通帳見てまたニヤけたわ。
副業で稼いだ10万円。しかも、自分の得意分野で。これはほんまに嬉しかった。
副業のその後
この案件がきっかけで、「営業用AIデモ作成サービス」っていう肩書きをつけて、クラウドソーシングでも仕事を募集するようになった。
今では月に1〜2件、営業支援用のAIデモを作る仕事を受けてる。
異常検知、チャットボット、レコメンド、画像分類…いろんな業種に応用できる。
副業を通じて、ワイは「会社の外でも通用するスキル」を実感できた。
収入も増えたし、自信もついた。何より、自分の技術が誰かの“売る力”になるって、めっちゃやりがいある。
というわけで、営業用AIデモ作成サービスでワイが10万円稼いだ話や。
もし同じように副業考えてるAIエンジニアがおったら、営業支援は狙い目やで。
技術を“見せる”っていうスキルは、意外と重宝される。
ワイみたいに、自宅で稼げるチャンスはゴロゴロ転がってる。あとは、拾うかどうかや。
さて、次はどんなデモを作ることになるんやろな。楽しみや。
アニメ・漫画の登場人物やゲームキャラクターの現在の年齢まとめ
X(旧Twitter)やYouTube、TikTok、SNSで話題の猫(ネコ、ねこ)情報まとめ
犬(ワンちゃん)を飼っている意外な有名人・タレント・芸人・インフルエンサー・YouTuberまとめ
TikTokで人気急上昇のTikToker(ティックトッカー)情報まとめ
スポンサーリンク
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d95674f.5ea53f98.4d956750.ba046f97/?me_id=1285657&item_id=12998944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01141%2Fbk4046071877.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

