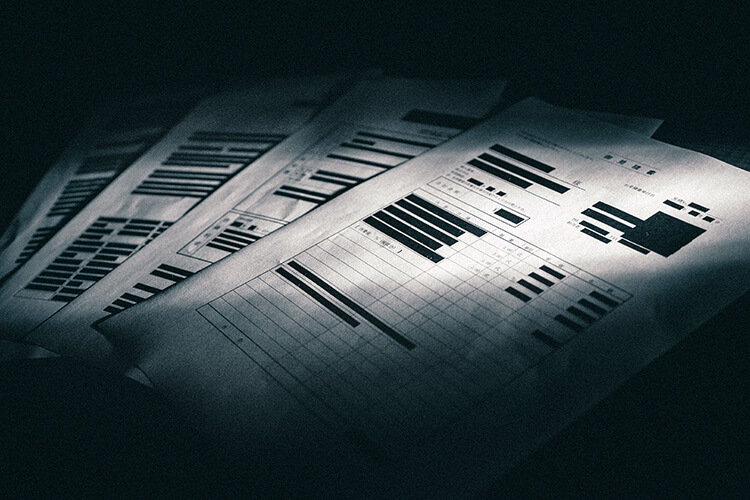
ワイは都内のIT企業で働く30代のAIエンジニアや。
普段は自然言語処理のモデル開発とか、企業向けのAIソリューションを作ったりしてる。
仕事はやりがいあるけど、正直、収入面ではもうちょい余裕が欲しい。
せやから、副業で何かできへんかとずっと考えてたんや。
きっかけは「翻訳と要約、誰かやってくれへん?」
ある日、Xでフォローしてるフリーランスのライターが「海外の資料を読むのがしんどい。
誰か翻訳と要約を定期的にやってくれる人おらんかな?」ってつぶやいてたんや。
ワイはそれ見て、「それ、AI使えば効率よくできるやん」って思った。
ワイの専門は自然言語処理。翻訳も要約も、今のモデルならかなり精度高い。
しかも、ちょっと人の手を加えれば、読みやすくて実用的なアウトプットになる。
そこで、DM送って「定額で翻訳・要約サービスやりますよ」って提案してみたんや。
そしたら「ぜひお願いしたい!」って即レス。そこから、ワイの副業が始まった。
サービス設計について
サービス設計は月額5,000円のサブスクモデル
最初は個別対応やったけど、効率悪いし収益も安定せえへん。せやから、サブスクモデルに切り替えた。内容はこんな感じや。
・月額5,000円
・毎週1回、指定された記事・資料を翻訳&要約(英→日 or 日→英)
・文字数は1回あたり最大3,000字まで
・納期は48時間以内
・Slackまたはメールで納品
このサービスをnoteとXで告知したら、意外と反応があってな。特に多かったのが、以下の層や。
海外のニュースや論文をチェックしたいけど、英語が苦手なビジネスパーソン
海外クライアントとのやりとりがあるフリーランス
英語教材を作ってる教育関係者
最初の1ヶ月で5人が契約してくれて、月収25,000円。自宅で、空いた時間にできる仕事としては上々や。
AI+人力のハイブリッドで品質を担保
もちろん、全部AI任せにはしてへん。
ワイはChatGPTやDeepLを使って、まず機械翻訳と要約を生成。そのあと、自分でチェックして、文脈に合うように修正する。
特に要約は、単に短くするだけやなくて「何が重要か」を見極める必要がある。
たとえば、ある週に依頼されたのは、海外のマーケティングレポート。AIに要約させると、数字ばっかり並んでて、読み手にとって「で、何が言いたいの?」ってなる。
そこをワイが補足して、「このレポートのポイントは、Z世代がSNS広告に対して反応しやすい傾向があること」ってまとめる。
こういう「人間の視点」が入ることで、クライアントの満足度がぐっと上がるんや。
口コミと紹介で契約者が増加
2ヶ月目には契約者が10人に増えて、月収5万円。
Slackで納品したときに「めっちゃ助かってます!」「これ、社内でも使いたい」って言われて、そこから法人契約にもつながった。
ある教育系スタートアップは、月額2万円で契約してくれて、毎週2本の教材記事を翻訳・要約。
しかも、社内で使うテンプレートも一緒に作ってほしいってことで、追加で3万円のスポット案件も受注した。
この月は、合計で10万円超え。
全部自宅で完結してるし、Zoomも使わへん。
Slackとメールだけでやりとりして、納品はGoogle Docs。
ほんまに、今の時代ってすごいわ。
工夫したポイントと学び
この副業でうまくいった理由は、いくつかあると思ってる。
・サブスクモデルで収益が安定
・AIを活用して作業効率を最大化
・人力で品質を担保して、信頼を獲得
・クライアントの業種に合わせて柔軟に対応
あとは、ワイが「現役AIエンジニア」って肩書きやから、信頼されやすかったのもある。
技術的な裏付けがあるってだけで、安心感が違うんやろな。
今後の展望
今は契約者が15人を超えてて、月収ベースで7〜10万円をキープしてる。
今後は、以下の展開を考えてる。
・自動化ツールの開発(依頼→納品までのフローを効率化)
・翻訳・要約テンプレートの販売
・法人向けの月額プラン(複数部署対応)
副業って、単に「稼ぐ」だけやなくて、自分のスキルをどう活かすかの実験場やと思う。
ワイはこの副業を通じて、「AIは使い方次第で、誰かの課題を解決できる」ってことを実感した。
というわけで、ワイの副業体験談、参考になったやろか?
AIエンジニアとしてのスキルを、ちょっと視点を変えて提供するだけで、ちゃんと価値になる。
ほんまに、今の時代は「技術×サービス」で稼げるチャンスがゴロゴロしてるで。
アニメ・漫画の登場人物やゲームキャラクターの現在の年齢まとめ
X(旧Twitter)やYouTube、TikTok、SNSで話題の猫(ネコ、ねこ)情報まとめ
犬(ワンちゃん)を飼っている意外な有名人・タレント・芸人・インフルエンサー・YouTuberまとめ
TikTokで人気急上昇のTikToker(ティックトッカー)情報まとめ
スポンサーリンク
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d95674f.5ea53f98.4d956750.ba046f97/?me_id=1285657&item_id=12998944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01141%2Fbk4046071877.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

