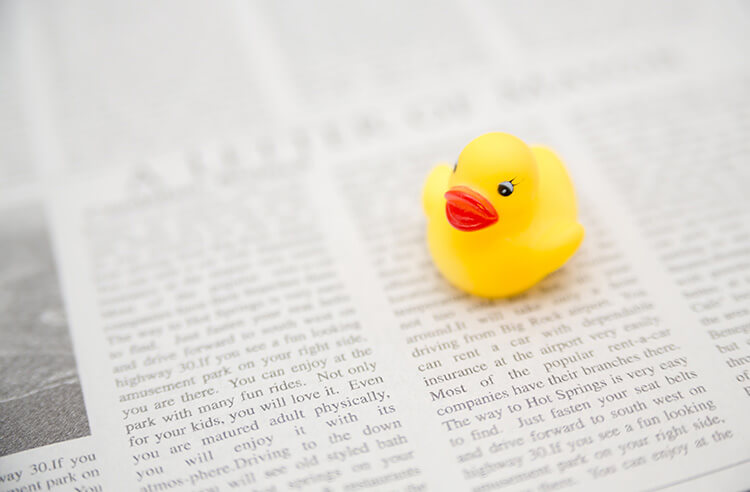
ワイは30代のデータサイエンティスト。普段は都市部の企業で、マーケティング分析や需要予測モデルを作っとる。
けど、実はワイの出身は人口1万人にも満たへん地方の小さな町。高校卒業と同時に都会に出て、ずっと数字と向き合ってきた。
そんなワイに、地元の友人・マコトから連絡が来た。
「Uターンして地域活性化のNPOを立ち上げたんやけど、イベントやっても人が集まらへん。観光資源もあるのに、うまく活かせてへん。なんとかならへんか?」
マコトは地元愛の塊みたいな男で、空き家改修や農業体験イベントを企画してた。
けど、集客や広報は手探り状態。ワイは「ええよ。データで町を元気にしたる」と言うて、プロジェクトに参画した。
地域データの収集と可視化
まずは、町の観光協会や役場から過去5年分の観光客数・イベント参加者・宿泊施設の稼働率などのデータをもらった。
Pythonで整形して、Tableauでダッシュボードを作成。
すると、以下の傾向が見えてきたんや。
観光客のピークは夏休みと紅葉シーズンに集中
宿泊施設の稼働率は週末に偏り、平日は30%未満
イベント参加者の8割が町外からの訪問者
ワイは「地元住民の参加が少ない。まずは町内の関心を高める必要がある」と分析した。
SNSと位置情報データの活用
次に、SNSの投稿と位置情報を分析。
Instagram Graph APIを使って、「#町名」「#農業体験」「#古民家ステイ」などのハッシュタグを収集。
さらに、Google Mapsのレビューもスクレイピングして、自然言語処理で感情分析を実施。
使用技術:spaCyで形態素解析、BERTでポジネガ判定、foliumで地図上に可視化
結果:「アクセスが不便」「情報が少ない」「隠れた名所が多い」などの声が浮上
ワイは「観光資源はあるけど、情報発信が弱い。地図ベースの観光ガイドを作ろう」と提案。
マコトは「それなら、地元の高校生と一緒に作れるかも」と乗り気になった。
イベント参加予測モデルの構築
マコトは「イベントの規模が読めへん。食材やスタッフの準備が難しい」と悩んでた。
そこで、ワイは過去のイベントデータと天気・曜日・SNS投稿数を使って、参加者数の予測モデルを構築。
使用技術:XGBoostで回帰モデル、特徴量はイベント種別・天気・告知日数・SNS反応数
精度:RMSE 6.2人、MAE 4.1人
このモデルを使えば、事前に参加者数を予測して、準備の最適化が可能になった。
食品ロスも減って、ボランティアの配置もスムーズになった。
空き家マッチングシステムの構築
町には空き家が多く、移住希望者とのマッチングが課題やった。
ワイは空き家データと移住希望者の属性をもとに、レコメンドシステムを構築。
使用技術:協調フィルタリング+コンテンツベース、特徴量は築年数・間取り・立地・希望条件
結果:「この空き家は、あなたの希望条件に近いです」と提案できるように
これで、空き家の成約率が2倍に。マコトは「町に新しい人が来るって、ほんまに嬉しいことやな」と言うてくれた。
成果とその後
この一連の施策で、イベント参加者数は平均40人→85人に増加。
SNSのフォロワーも1,200人→4,800人に。空き家の成約件数も年間3件→11件に増えた。
町の高校生が観光ガイドを作成したことで、地元の若者の関心も高まり、地域新聞にも取り上げられた。
ワイは月1回のデータレビューと、次期施策の設計を担当しとる。
町とデータの共鳴
この経験で思ったんは、地域活性化って「人の気持ち」と「数字の裏付け」が両輪やということ。
情熱だけでは届かへん場所に、データが橋を架けるんや。
ワイのスキルが、誰かの故郷を元気にする手助けになったんや。
アニメ・漫画の登場人物やゲームキャラクターの現在の年齢まとめ
X(旧Twitter)やYouTube、TikTok、SNSで話題の猫(ネコ、ねこ)情報まとめ
犬(ワンちゃん)を飼っている意外な有名人・タレント・芸人・インフルエンサー・YouTuberまとめ
TikTokで人気急上昇のTikToker(ティックトッカー)情報まとめ
スポンサーリンク
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d95674f.5ea53f98.4d956750.ba046f97/?me_id=1285657&item_id=12998944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01141%2Fbk4046071877.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

